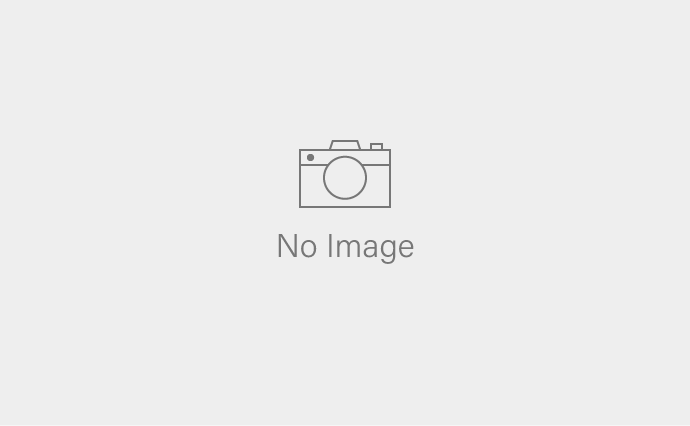生物という科目
全体のイメージ
大学受験において、生物は暗記のイメージが強い科目です。 理系の人であれば「物理+化学」か「化学+生物」かで悩んで、計算を避けるために生物を選ぶという人も少なくないはずです。 これは半分正解、半分間違いです。生物は大学によって、イヤな言い方をすれば偏差値帯によって、問題の感じがガラッと変わる科目です。
偏差値55より下の大学・学部は、暗記で何とかなる場合が多いです。 55はあくまでも目安ですが、日東駒専、産近甲龍、それらより偏差値が下の大学のイメージです。 このレベル帯だと、用語を問う問題、正誤問題、4択問題などがメインになってきます。 基本事項の暗記を徹底すれば、何とかなるレベル帯とも言えます。
偏差値55を超えると、暗記で何とかならない場合が多くなります。 何とかならない理由その1は「問われる知識自体がマニアックになる」こと。 私立大学、特に医学部に多い傾向です。 理由その2は「実験考察系問題が出題される」ことです。 国立の、いわゆる難関大学に多い傾向です。 これについては、この後に詳しく説明していきます。
もちろん、偏差値だけで比べることはできませんが、自分の志望校の過去問は早めに確認し、傾向をつかんでおく必要があります。 特に、実験考察問題が難しい大学は、早い時期から理論的な考え方の練習をしておかないと、大問1つまるまる捨てることになりかねません。
共通テストの生物
高得点を狙う人にとって、共通テストの生物はかなりの強敵です。 共通テストが始まった年からの平均点は72.64(令和3)→ 48.81(令和4)→ 48.46(令和5)→ 54.82(令和6)→ 52.21(令和7)と推移しています。 特に令和5年度の48.46点は得点調整後の点数です。 調整前の平均点は39.74点です。 令和6年以降は50点台で推移していますが、共通テストが始まって以降、平均点の乱高下が続いています。 あと数年、平均点50点前後が続けば「落ち着いたかな」とも思えるのですが、まだまだ油断ができません。
油断ができない以上、一番難しかった年の過去問が解けるレベルを目指して勉強するしかありません。 そこで最大の敵となるのが実験考察問題です。 学校の教科書に載っていないことが出題されます。 どこの出版社の教科書にも載っていません。 ある意味、平等です。ただ、単なる意地悪問題ではなく、解答の根拠となる実験データや資料は与えられています。 高得点を狙う人はそれらを読み解き、解答する練習が不可欠です。
一般入試の生物
上で書いたとおり、ある程度の大学までは暗記で何とかなります。 共通テストが始まってから、いろいろな大学で実験考察系「もどき」の問題が出題されていますが、よくよく読んだらただの知識問題だったりします。 もちろん、「もどき」を見極めるためにも正確な知識は必要です。
ある程度「以上」の大学、GMARCH、関関同立、中堅国立大学以上になると、暗記したことを「活用する」力が求められます。 実験考察問題+記述問題によって、本質を理解している人とそうでない人がバッサリ分かれます。 私立医学部などではマニアックな知識も問われますが、それ以上に必要とされているのが「科学的なものの見方」です。 物理や化学でもそのような傾向はありますが、特に顕著なのが生物です。 上を目指す人は、それなりの覚悟を持って受験勉強に臨みましょう。
生物基礎と生物
生物とほかの科目(化学、物理)の大きな違いとして、生物基礎でしか出てこない分野がある、ということがあげられます。 具体的には「体内環境・恒常性(ホルモンや免疫など)」の分野です。 化学や物理は基礎科目の内容を発展させて専門科目の内容になっています。 極端な話、化学や物理が理解できていたら、化学基礎や物理基礎は不要です。 ところが、生物(基礎じゃない方)はホルモン、免疫の内容を含んでいません。 生物基礎で習いっぱなしです。
共通テストは「生物」なのでホルモンや免疫は出題されません。 が、私立の一般入試や国公立の二次試験では出題範囲が「生物基礎・生物」となっている場合がほとんどです。 当然のようにホルモンや免疫が出題されます。 共通テスト対策を一生懸命やった人ほど、ホルモンや免疫が手薄になっている場合があります。 十分気を付けてください。
勉強の進め方
高校1年生、2年生の人向け
生物基礎、生物は学校の勉強をがんばってください。 それに尽きます。基本事項のインプットは学校の授業をフル活用しましょう。 定着の確認は定期テストに任せましょう。 毎回70~80点を狙うつもりでがんばってください。 ただし、2年生のうちに(遅くとも3年生の夏休みまでに)全範囲が終わらないようであれば、先取り学習も検討していきましょう。
先取り学習をするのであれば、あとで紹介するインプット用の参考書を使ってみてください(自力で教科書を理解できるのであれば不要です)。 余裕がある人はアウトプット用の問題集を試してみてもいいかもしれません。 が、この時期に大切なのは国語、数学、英語です。 これら3科目がきちんとできたうえで、理科や社会をがんばってください。 くれぐれも優先順位を間違えないように。
高校3年生の人向け
いよいよ受験の年です。 学校の授業で全範囲が終わりそうにない場合は、夏休みを利用して全範囲をサラッと先取りしてもいいと思います。 もう一つ大切なのは、志望校の過去問に目を通しておくこと。 暗記と実験考察問題の割合、暗記はどのレベルまで求められるのか、記述かマークか、配点は、など、入試本番までに到達しなければならないレベルを把握しておきましょう。 これは、学校の生物の先生や塾の先生にも見てもらってください。 決して安易な自己判断をしないように。
そしていよいよ実戦練習です。 アウトプット用の問題集を使って、入試レベルの問題に慣れていきましょう。 学校でエクセルやセミナーなどの問題集が配られている場合、それらが大活躍してくれます。 だいぶ前に習ったところも覚えているか確認しながら進めます。 解答の根拠もきちんと言えるかどうか、ちょっとでも不安なところは解説をしっかり読み込んでください。 学校で配られる問題集も、最近は解説がしっかりしているものが多く、なかなか頼りになります。 学校の問題集をやりきった、または配られていないという人は、生物基礎問題精講(旺文社)がおススメです(詳しくは後ほど)。 ただ、学校で配られる問題集が生物重要問題集(数研出版)なのであれば、注意が必要です。 かなり難しいです(これも詳しくは後ほど)。 大切なのは自分のレベルにあった問題集を使うことです。 重要問題集の解説が理解できず、時間を取られるくらいなら、基礎問題精講を2周も3周もした方が定着度も上がります。
偏差値55くらいまでの大学なら基礎問題精講から過去問、55以上であれば重要問題集を挟んで過去問という流れになるかと思います。 基本的に教科書、学校の問題集or基礎問(志望校によっては重問)、過去問でケリをつけたいところです。 ほかの科目で問題集ドッサリですもんね。 この後でいろいろ紹介しますが、あまり深入りしないことが大切です。 暗記メインの科目に深入りすると底なし沼です。
参考書・問題集
インプット用(講義系参考書)
教科書(東京書籍、啓林館など): 参考書ではありませんが、教科書はすべての基本です。 わからないことがあったら、必ず戻ってきましょう。 出版社による掲載内容の違いはほとんどありません。 まず自分の教科書を頭に入れることを目指しましょう。
資料集(数研出版など): 学校で配られているなら、最大限活用してください。 配られていないなら、購入を検討してみてください。 一般の書店で販売されています。 教科書より踏み込んだ内容まで載っているので、目を通しておいて損はありません。 実験考察問題の土台を作るには最適の教材です。
山川の生物が面白いほどわかる本(KADOKAWA)など: 基本的に生物の講義系参考書は不要だと思います。 教科書と資料集で十分です。 教科書の内容が理解できないときに検討してみてください。 この本にこだわる必要はないので、本屋さんでパラパラ眺めてみて、自分が読みやすいものが一番です。
大森徹の最強講義126講(文英堂): 講義系参考書というよりは辞書。 多くの受験生にとって、ここまでの知識は不要です。 すべてを熟読する時間はないと思いますので、わからないところを調べるという使い方がメインになります。 難関大を目指す、生物を得点源にしたい人は購入を検討する価値ありです。 生物が好きな人は、持っているとテンションが上がります。
アウトプット用(問題集)
生物入門問題精講(旺文社): この後に紹介する基礎問題精講が難しいと感じる人向けの問題集です。 学校で配られる問題集よりも少し解説が詳しいくらいなので、そちらでも代用できます。 あまり購入する必要を感じません。
生物基礎問題精講(旺文社): 個人的には一番のおススメです。 入試で生物を使う人は、このレベルを確実に解けるようにしてもらいたいと思います。 タイトルに「基礎」とついていますが、この問題集の内容が完璧に理解できていれば、偏差値55~60くらいの実力だと思います。 使うときの注意点としては、問題を解いて終わりではなく、解説もきちんと読んで、理解をしてもらいたいということです。 その問題を題材として、周辺知識も確認できるようになっているので、繰り返し読んでもらいたいと思います。 下記のリンクも参考にしてください。
https://note.com/high_koh/n/n456119ab14a8
生物標準問題精講(旺文社): かなり難しいです。 全然「標準」じゃありません。 基礎問が完璧になった人で、生物を得点源にしたい人は挑戦してもらいたいと思います。 が、多くの受験生についてはオーバーワークです。 ほかの科目との兼ね合いもあるので、生物にどこまで時間を使えるかを考えながら、進めてもらいたいと思います。 志望校の過去問を見て、頻出分野だけ勉強するのもアリだと思います。
生物重要問題集(数研出版): 控えめに言って神です。 学校で配られたら超ラッキー、配られなくても購入を検討してもらいたい一冊です。 個人的には基礎問→重問で、たいていの大学は何とかなると思っています。 A問題とB問題に分かれているので、基礎問が終わった人はまずA問題に挑戦してみてください。 A問題なのに記述もあれば計算もあり。 なかなか歯ごたえがあります。 B問題まで手を出すかは、残り時間とほかの科目との相談になります。 A問題とB問題に分かれている分、自分の現状に合わせた使い方ができるので、その点で標準問題精講より使いやすいと思います。 これだけで記事を一本書きたくなるくらい、おススメな問題集です。でもまずは基礎問。
https://note.com/high_koh/n/n8d25d61b0c7a
大森徹の生物 遺伝問題の解法、計算・グラフ問題の解法、実験・考察問題の解法、記述・論述問題の解法(4冊いずれも旺文社): 大学の出題傾向や自分の苦手分野などを見て、使用を検討します。 が、多くの受験生はここまでやる時間がないのではないでしょうか。 興味がある人は本屋さんで眺めてみてください。
まとめ
全体を通して言えることは、まず英語や数学をがんばれ、ということです。 正直、生物にあまり時間をかけられない受験生の方が多いのではないでしょうか。 とはいえ生物は基本的には暗記科目、知らないことが出てくると不安になってあれもこれも…となるのが受験生の心情です。 なので、「この一冊だけは完璧にする」という気持ちで生物に向き合ってもらいたいと思います。 当面の目標は生物博士になることではなく、大学生になることのはずです。 「この一冊」というのは基礎問題精講の人もいれば、重要問題集の人もいると思います。 過去問をきちんと分析し、今の自分にとって、合格のために、何をどこまでやればいいのか、そこをハッキリさせる必要があります。 学校の生物の先生や塾の先生を最大限活用して、がんばってもらいたいと思います。
実験考察問題や記述問題の対策、重要問題集の魅力や使い方など、まだまだ書きたいことがたくさんあります。 今後も少しずつ記事にしていきたいと思いますので、時々でも覗いていただければと思います。